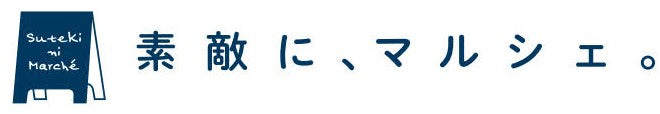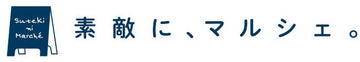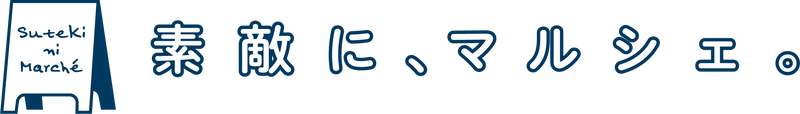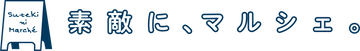塩分はなぜ身体に悪い?塩分の多い食べ物と注意すべきポイント

1. はじめに
1-1. 塩分とは?私たちの体に必要なミネラル
塩分(塩化ナトリウム)は、私たちの体にとって欠かせないミネラルの一つです。 体内の水分バランスを調整し、神経や筋肉の機能を維持する重要な役割を持っています。
塩分の主な働き:
- 体内の水分バランスを維持 ~ ナトリウムは細胞の浸透圧を調整し、水分の移動を助ける
- 神経や筋肉の働きをサポート ~ 適量の塩分が、神経伝達や筋肉の収縮に必要
- 血圧の調整に関与 ~ 塩分の摂取量によって血圧が上下する
このように、塩分は私たちの健康を維持するために不可欠な成分ですが、摂りすぎると健康リスクが高まることが知られています。

1-2. 取りすぎるとどうなる?塩分過多がもたらす健康リスク
塩分は適量であれば問題ありませんが、摂取量が多くなると高血圧や腎臓への負担、むくみなどのリスクが高まります。 特に、日本人は塩分を多く摂取しがちで、厚生労働省の調査によると1日の推奨摂取量(男性7.5g・女性6.5g)を超える人が多いと言われています。
塩分を摂りすぎることで起こる主な健康リスク:
- 高血圧 ~ 血圧が上がり、心臓病や脳卒中のリスクが増加
- 腎臓への負担 ~ 腎臓がナトリウムを排出しきれず、機能低下の原因に
- むくみ ~ 塩分が水分を溜め込みやすくし、顔や足がむくむ
- 骨への影響 ~ カルシウムの排出を促し、骨粗しょう症のリスクが上がる
こうしたリスクを回避するためには、塩分を控えた食生活を意識することが大切です。 では、塩分が多い食べ物にはどのようなものがあるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
2. 塩分の多い食べ物とは?
2-1. 加工食品(ハム・ソーセージ・インスタント食品) ~ 手軽だけど塩分が高め
加工食品は手軽に食べられる反面、保存性を高めるために塩分が多く含まれていることが特徴です。 特に以下の食品には注意が必要です。
- ハム・ソーセージ・ベーコン: 100gあたり2~3g以上の塩分を含む
- インスタントラーメン: 1食あたり5~6gもの塩分を含むことも
- カップスープやレトルト食品: 味を濃くするために多くの塩分が使われている
特にインスタントラーメンはスープに塩分が多く含まれているため、スープを残すことで塩分摂取量を減らせるという工夫も可能です。

2-2. 調味料(醤油・味噌・塩) ~ 料理に欠かせないけれど使いすぎ注意
日本の食文化には醤油・味噌・塩などの塩分が多い調味料が欠かせません。 これらは料理の味を引き立てる重要な要素ですが、使いすぎると塩分過多になってしまいます。
- 醤油: 小さじ1杯(5ml)で約1gの塩分
- 味噌: 大さじ1杯(18g)で約2gの塩分
- 塩: 小さじ1杯(6g)で約6gの塩分
減塩醤油や出汁を活用することで、塩分を控えながら美味しさを保つことができます。
2-3. スナック菓子・ファストフード ~ 知らず知らずに塩分過多になる落とし穴
スナック菓子やファストフードも塩分が多く、気づかないうちに塩分を摂りすぎてしまうことがよくあります。
- ポテトチップス: 1袋(60g)で約0.8~1.2gの塩分
- フライドポテト: 1食で約1~2gの塩分
- ハンバーガー: 1個で約1.5~2gの塩分
また、チーズやベーコンを使ったファストフードは特に塩分が高くなりがちです。 塩分の少ないスナック(ナッツや無塩ポップコーン)を選ぶことで、塩分摂取を抑えることができます。
塩分の多い食品を知ることで、日常の食事から塩分を少しずつ減らす意識が持てます。 次の章では、塩分を摂りすぎるとどのような影響が出るのか、詳しく解説します。
3. 塩分の過剰摂取による影響
3-1. 高血圧のリスク ~ 血管に負担をかけ、心臓病の原因に
塩分を摂りすぎると高血圧のリスクが高まります。 ナトリウムは体内の水分を保持する働きを持っており、塩分を多く摂取すると血液量が増えて血圧が上昇します。
高血圧の主なリスク:
- 動脈硬化の進行: 血管が硬くなり、血流が悪くなる
- 心臓への負担増加: 高血圧が続くと心臓病のリスクが高まる
- 脳卒中の危険性: 血圧が高いと脳の血管が破れやすくなる
特に日本人は塩分を摂りすぎる傾向があるため、日々の食事で減塩を意識することが重要です。
3-2. むくみ・腎臓への負担 ~ 体内の水分バランスが崩れる
塩分を摂りすぎると体内の水分バランスが崩れ、むくみや腎臓への負担が増します。
- むくみ: 余分な塩分が水分を引き寄せ、顔や足が腫れるような症状
- 腎臓への負担: 体内のナトリウムを排出するために腎臓が過剰に働く
特に腎臓の機能が低下している人は、塩分を控えることが推奨されます。 また、水分をしっかり摂ることで、塩分の排出を促すことができます。
3-3. 骨への影響 ~ カルシウムの排出を促し、骨粗しょう症のリスクも
塩分を摂りすぎると、尿と一緒にカルシウムが排出されやすくなることが分かっています。 これが長期間続くと、骨が弱くなり、骨粗しょう症のリスクが上がる可能性があります。
特に女性や高齢者は骨密度が低下しやすいため、塩分の摂取を適度に抑えることが大切です。
4. 塩分を控えるためのポイント
4-1. 減塩調味料を活用する ~ 醤油・味噌・塩の代替アイデア
調味料は料理に欠かせませんが、減塩タイプの調味料を選ぶことで塩分を抑えることができます。
- 減塩醤油: 通常の醤油と比べて約50%の塩分カット
- 減塩味噌: 味噌汁や和え物に使う際に便利
- レモンや酢: 酸味を加えることで塩分控えめでも美味しく感じる

塩の代わりに出汁やハーブを活用することで、風味を損なわずに美味しい料理を作ることができます。
4-2. 出汁やスパイスで味付けを工夫 ~ 塩分を控えながら美味しさアップ
塩分を減らしながら料理の美味しさを保つためには、出汁やスパイスを上手に使うのがポイントです。
- 昆布・鰹節の出汁: 天然の旨味を活かして減塩
- ニンニク・生姜・ごま油: 風味をプラスして満足感アップ
- スパイス(胡椒・カレー粉): ピリッとした刺激が味を引き締める
減塩=味が薄くなるわけではないので、調理方法を工夫することが大切です!
4-3. 外食や加工食品の塩分をチェック ~ 知っておきたい塩分量の目安
外食や加工食品には知らないうちに多くの塩分が含まれていることがよくあります。 そのため、外食時や市販品を選ぶ際には、塩分量の目安を把握しておくことが重要です。
- ラーメン1杯: 約5~7gの塩分
- 牛丼1杯: 約3~4gの塩分
- カップ麺: 1食あたり5~6gの塩分(スープを飲み干すとさらに増加)
塩分控えめのメニューを選ぶ、スープは残す、などの工夫をすることで塩分摂取量を減らすことができます。
5. まとめ
5-1. 塩分を控えることで健康リスクを軽減できる!
塩分は体にとって必要な成分ですが、摂りすぎると高血圧や腎臓病、骨の健康に影響を与える可能性があります。 日々の食生活を見直し、適量の塩分を意識することが重要です。
5-2. 無理なく減塩を続けるために、日々の食生活を工夫しよう
- 減塩調味料を活用する
- 出汁やスパイスで味に深みを加える
- 外食や加工食品の塩分を意識する
「減塩=我慢」ではなく、美味しく続けられる工夫を取り入れることで、健康的な食生活を無理なく続けられます。 今日からできることを少しずつ始めてみましょう!