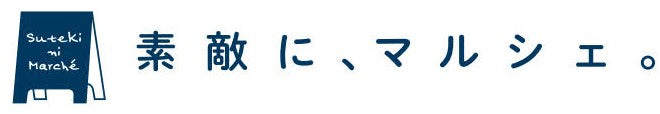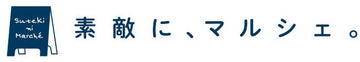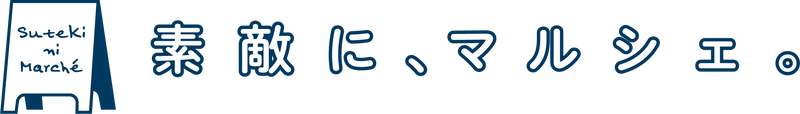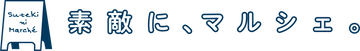刺身の「つま」は食べてもいい?その由来と役割を解説

1. はじめに
1-1. 刺身の横にある「つま」、食べる?食べない?
お刺身を食べるとき、横に添えられている「つま」をどうしていますか? 大根の千切りやシソの葉、ワカメなどが盛り付けられていますが、食べるべきなのか、ただの飾りなのか迷ったことがある人も多いはず。
「つま」は、単なる飾りではなく、昔からさまざまな役割を持って添えられてきました。 本記事では、つまの由来や意味、食べてもいいのかどうかを詳しく解説していきます!

1-2. 実は奥深い「つま」の歴史と役割
「つま」は、ただ刺身を引き立てるためにあるのではなく、食文化の中で重要な意味を持つ存在です。 食中毒予防や風味を高める効果もあることから、昔の人たちは自然の知恵として「つま」を取り入れていました。
また、地域やお店によって異なる「つま」が使われることもあり、そのバリエーションは非常に豊富。 意外と奥が深い「つま」の世界を、一緒に見ていきましょう!
2. 「つま」の由来とは?
2-1. そもそも「つま」って何?
「つま」とは、刺身の横や下に添えられている薬味や飾りのことを指します。 一般的には、大根の千切り、シソの葉、ワカメ、海藻類、紅たでなどが使われます。
「つま」という言葉は「端(つま)」に由来し、「添え物」「脇役」という意味があり、刺身の引き立て役として重要な存在となっています。

2-2. 昔の人はなぜ「つま」を添えていたのか?
昔の人たちは、刺身をより安全に美味しく食べるために「つま」を添えていました。 冷蔵技術が発達していなかった時代、刺身はすぐに傷んでしまうため、食中毒のリスクがありました。
そこで、「つま」として抗菌・殺菌作用のある食材を一緒に盛り付けることで、食中毒を防ぐ役割を果たしていたのです。 例えば、シソの葉には抗菌効果が期待できるので、刺身の下に敷かれることが多いのはこのためです。
2-3. 日本各地で異なる「つま」の種類
地域ごとに「つま」の種類は異なります。以下のように、地方ごとに特徴的な「つま」が使われています。
- 関東:大根の千切り、シソの葉、紅たで
- 関西:ワカメやもみじおろし
- 九州:ケン(大根の細切りに加え、青じそやネギ)
- 北海道:昆布、がごめ昆布
このように、地域によって刺身の「つま」に使われる食材が異なるのも興味深いポイントですね!
3. 「つま」の役割と意味
3-1. 刺身を美しく見せるための飾りとしての役割
「つま」は、刺身を美しく盛り付けるための重要な役割を担っています。 シンプルな刺身だけでは単調な見た目になってしまうため、色鮮やかな「つま」を添えることで華やかさが増します。
特に、白身魚には大根の千切り、マグロには紅たでなど、刺身の色合いに合わせた「つま」が工夫されていることが多いです。
3-2. 食中毒予防?殺菌・防腐効果のある「つま」
「つま」は、単なる飾りではなく、食中毒を防ぐ役割も持っています。 例えば、以下のような食材には殺菌作用や防腐作用があります。
- シソの葉:抗菌作用があり、細菌の繁殖を防ぐ
- わさび:強い抗菌・防腐作用があり、刺身の鮮度を保つ
- 大根の千切り:水分を適度に吸収し、食感の調整に役立つ

特に生魚を食べる文化のある日本では、「つま」をうまく活用することで、安全に美味しく食べる知恵が受け継がれてきました。
3-3. 口直しや風味アップ!「つま」が持つ味の効果
「つま」には、刺身の味を引き立てる役割もあります。 例えば、脂の多い魚を食べた後に大根の千切りを食べると、口の中がさっぱりします。
また、紅たでやもみじおろしは、刺身にアクセントを加え、より風味豊かに楽しめる効果があります。 刺身を食べる際に「つま」を一緒に食べることで、より美味しく味わうことができるのです!
4. 「つま」は食べてもいいの?
4-1. 「つま」を食べる派 vs. 食べない派の意見
刺身の「つま」は食べてもいいのか?この問いに対しては、意見が分かれることが多いです。 食べる派・食べない派、それぞれの意見を見てみましょう。
【食べる派の意見】
- 「大根の千切りがさっぱりしておいしい!」
- 「シソの葉や紅たでは風味が良く、刺身と一緒に食べると美味しい」
- 「健康に良い成分が含まれているので、食べるべき!」
【食べない派の意見】
- 「飾りだと思っていたので、食べる習慣がない」
- 「魚のニオイが移っていて美味しくないことがある」
- 「居酒屋などでは衛生面が気になる」
「つま」は本来、食べることを前提に作られていますが、環境や個人の好みによって意見が分かれるようです。
4-2. 食べてもOKな「つま」と食べないほうがいい「つま」
実は「つま」には、食べてもOKなものと、食べないほうがいいものがあります。 以下を参考に、どの「つま」が食べられるのかチェックしてみましょう。
【食べてもOKな「つま」】
- 大根の千切り
- シソの葉
- 紅たで
- ワカメ
- もみじおろし
【食べないほうがいい「つま」】
- 乾燥昆布(味付けされていないもの)
- 店舗によっては、長時間空気に触れているもの
基本的に「つま」は食べても問題ありませんが、鮮度が落ちたものや、衛生面が気になる場合は避けたほうが良いでしょう。
4-3. お店の「つま」はどこまで食べてもいいの?
お店で提供される「つま」は、基本的には食べても大丈夫です。 ただし、刺身の下に敷かれている「つま」は魚の水分を吸っていることが多く、食感が悪くなっている場合もあるため、気になる場合は避けてもOK。
また、ファミレスやスーパーの刺身についている「つま」は、長時間空気に触れているため、風味が落ちていることもあります。 おいしく食べるなら、鮮度の良い状態の「つま」を選ぶのがポイントです。
5. 刺身をもっと楽しむ!「つま」の活用アイデア
5-1. 家庭での「つま」活用法(サラダや汁物へのアレンジ)
お店で出された「つま」を食べるのに抵抗がある方でも、家庭で作る「つま」はアレンジして楽しむことができます!
- 大根の千切り → サラダに混ぜて食感を楽しむ
- ワカメや海藻 → 味噌汁や酢の物に活用
- シソの葉 → 刻んでご飯に混ぜる、天ぷらにする

「つま」は単体で食べるよりも、料理にアレンジすることで、よりおいしく楽しむことができます!
5-2. 刺身の「つま」をおいしく食べるおすすめの食べ方
「つま」をそのまま食べるのも良いですが、ちょっとしたアレンジを加えるとさらに美味しく楽しめます。
- ポン酢やごま油をかけて、即席おつまみに
- わさび醤油で和えて、さっぱり副菜に
- 酢の物やナムル風にして食べる
ただ添えてあるだけではもったいない!「つま」を美味しく食べる方法を試してみてください。
5-3. 刺身に合う「つま」を自分で用意してみよう
家庭で刺身を食べる際に、自分で「つま」を用意するのもおすすめです。 スーパーで売っている刺身には大根の千切りだけが入っていることが多いですが、いくつかの種類を加えることで、さらに刺身を楽しめます。
- 大根の千切り+シソの葉で風味アップ
- 紅たでやもみじおろしでアクセントを加える
- ワカメや海藻を添えて、栄養価もプラス
自宅でもお店のような豪華な刺身盛りを再現してみましょう!
6. まとめ
6-1. 「つま」は食べるだけじゃない!見た目・風味・安全面で重要な存在
刺身の「つま」は、見た目を美しくするだけでなく、抗菌作用や風味アップなどさまざまな役割を果たしています。 また、食中毒のリスクを減らすための知恵としても活用されており、日本の食文化には欠かせない存在です。
6-2. 刺身をより楽しむために、「つま」をもっと活用しよう!
- 「つま」は基本的に食べてもOK!ただし衛生面には注意
- 家庭でのアレンジ次第で、さらに美味しく活用できる
- 刺身の味を引き立てる存在として、上手に使いこなそう
刺身を食べる際には、「つま」も一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか? いつもの食卓が、ちょっと特別なものになるかもしれません!